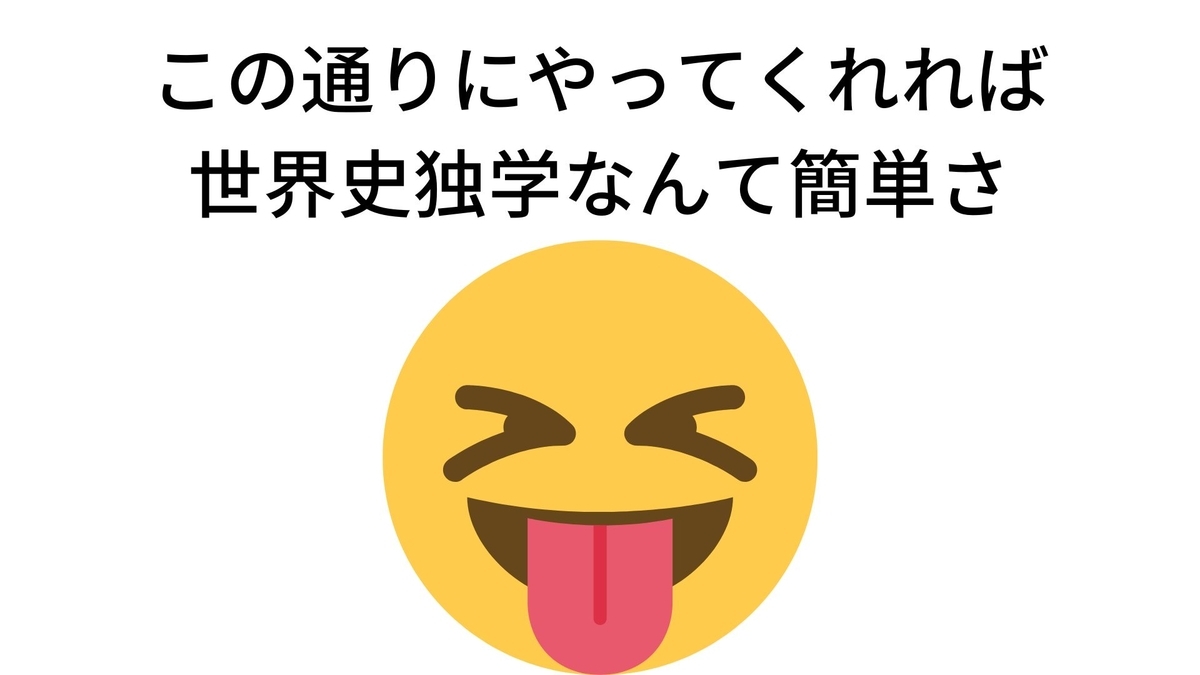
世界史の独学は非常に簡単です。
まあ日本史だってそう。
世界史・日本史ほど、
独学が向いている科目はない。
そう思うほどです。
「地頭」も「始める時期」も関係ありません。
誰でも簡単に短期間でも高偏差値を取れる。
僕は受験勉強を始めるまで、
楊貴妃という用語しか知りませんでした。
何でそれだけ知っていたのか・・・
自分でも分かりませんw
でも、それ以外は何も分からない。
正真正銘ゼロからのスタートです。
それでも1日たった2時間の独学で劇的に変わりました。
偏差値74(河合塾全統記述)。
慶應法で8~9割以上。
大して労せず取れるようになった。
とはいえ、そんなに上手くいかない人も多いようです。
独学でも塾に通っても、
結局伸びない人は伸びない。
これもまた真理でしょう。
もしあなたが僕と同じように、
世界史を独学で学ぶのであれば、
是非力にならせてください。
難しい事なんて1つもありません。
今回はゼロからできる独学勉強法を紹介します。
お伝えする通りに進めてくれれば、
いとも簡単に偏差値が上がり、
高得点・偏差値が取れるようになりますよ。

初めに:この記事の信ぴょう性
これでも独学難しいって思う?

僕はゼロから世界史の勉強を始めて、
河合全統記述では偏差値74、
早慶でも8~9割以上取れるようになりました。
1日2時間の独学によってです。
ここまでは冒頭の通り。
でも、あなたはこう思ったかもしれません。
「そんな上手く行くか?」
「自分にもできるのか?」
でも安心してください。
あなたにも絶対に出来ることだから。
こう言うのには根拠があります。
僕は今受験生に指導させて頂いていますが、
みなさんすこぶる成績を上げておられるんです。
例えばその内の一つはこれ⇩

他にも早大プレや慶大プレで一桁や、
予備校に行き続けて偏差値45から、
3か月弱で慶應合格するなど。
※この方々の模試成績や合格体験記はこちら
⇩
⇩
⇩
詳しく確認する
僕だったから出来たとかではない。
僕が教えている人も独学で、
もしくは予備校から独学に切り替えて、
ガンガン成績を上げている。
これでも独学難しいって思います?
独学やると難しいとか、
時間が掛かるなんて嘘。
みんなそのやり方を知らないだけ。
僕の教え子がそうだったように、
あなたにだって出来ることです。
その再現性は高いと言い切れるし、
ゼロからであっても短期間で仕上げられる。
僕自身の受験勉強時の経験からも、
これまでに教えてきた経験からも、
その知見を本記事に落とし込みました。
だから大船に乗ったつもりでご覧頂き、
取り組んで貰えたらと思います。
独学なんて簡単だし、
なんなら予備校より早く出来るようになりますよ。
また僕の教え子たちが成績爆上げした、
誰でもマネできる”社会勉強マニュアル”を、
公式ラインにて無料配布中です。
成績上げるのなんて一瞬。
世界史を一気に「超得意」に変えてしまってください。
世界史独学のコツ
目標設定を明確に

世界史を独学で勉強する際、
自らの目標を明確に定めておく必要があります。
「志望校で合格点を取れるようになる」
受験勉強をするからには、
これが大前提にはあるでしょう。
ただその志望校に応じて、
問題の”レベル”が違うのは当然ですね。
そして問題の”性質”も異なります。
たとえばMARCHと早慶では、
問題の”レベル”が異なります。
そして早慶と難関国立大学では、
問題の”性質”が異なります。
最終ゴールである問題のレベルや性質が違えば、
求められる勉強も変わってきます。
独学をする以上は、
自分で勉強する内容を決めなければなりません。
自分のゴールに対して適切な勉強内容が変わる以上、
まず初めにゴールの設定をしておきましょう。
ちなみに僕は私立文系受験です。
それに伴い慶應法をはじめ私立大学の世界史は、
超特急で攻略できますが国公立は正直分からないです。
なので本記事では原則、
「私立志望の人におススメ」になります。
国公立志望の人でも、
偏差値70以上を取るところまでは、
大いに役に立てると思います。
そこからは私立寄りの内容になっているので、
途中で切り上げて貰っても良いかもしれません。
ちなみに僕は私立世界史・日本史に対しては圧倒的に独学推奨です。
一方で国立志望の人は塾に通うことを、
検討しても良いのではないかとも思っています。
「私立世界史・日本史が独学推奨である理由」
これは別記事にまとめています。
⇒世界史・日本史は塾なし独学?それとも行くべき?判断基準は試験との相性
目標達成のために必要なことだけやる

目標が決まったらそれに伴い、
自分が今後何をやるべきかも決まってきます。
例えば難関私立なら、
難易度の高い用語まで覚える必要があるでしょう。
国公立なら論述を意識して、
体系的な理解を求めた学習や、
論述の練習もする必要があるかもしれません。
論述の対策必要ないのに、
論述を意識した勉強をする。
難易度の高い用語を覚える必要ないのに、
そこを意識して勉強する。
そんなことしても仕方ないですよね?
決めたゴールに対して、
必要な勉強のみやるようにしましょう。
それが目標に最短距離で走ることに繋がります。
巷では必要とされていることが、
あなたに必ずしも必要かどうかは分かりません。
みんながやっている事でも、
あなたには必要ないかもしれません。
まさに他人は他人、
自分は自分。
他の人が何をしているかなんて関係ない。
せっかく独学で自分に裁量がある訳ですよね。
その利点はフルに生かすべき。
自分の偏差値向上や志望校合格に直結する。
そういうことだけやるようにしましょう。
そこを見失うと・・・
独学で自分に裁量がある故に無駄な勉強を重ね、
迷走することになってしまいます。
下段から本題に入っていきます。
僕がやっていた独学世界史勉強法の流れ
独学の流れ
まずはこれから説明する、
独学の大まかな流れから。
0. 注意事項:流れを把握するなどの学習はしない
⇩
1. 通史問題集でゼロからスタート⇒基礎(偏差値70やMARCH合格レベル)
⇩
2. 高度な問題集による難関大学対策⇒あらゆる私立大学の試験に対応可能な上級者
⇩
3. 過去問⇒志望校余裕レベル
⇩
4. 最後の詰め⇒志望校で世界史が確実に強力な得点源になる
こんな流れになります。
それぞれについて以降で詳しく説明します。
ただ2,3,4については人に依ります。
全員がそこまではやる必要が無かったり、
時間的にできなかったりすることもある。
上記はあくまで理想だと思ってください。
半年以上勉強する時間があれば、
全てを余裕で全てをこなせます。
「残り2か月しかない」
「けどゼロからどうにかしたい」
こういう場合は状況に応じてやる事を変える必要はあります。
その辺りはケースバイケースでの判断にならざるを得ません。
自分の状況を鑑みて判断するようにしてくださいね。
※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!
【時間の無駄】流れを学ぶためだけの勉強はしない

世界史の勉強の初めの一歩として、
よくおススメされているのが、
「大まかな流れを理解する」ということです。
教科書や流れをまとめられた参考書。
こういったものを使って学ぶことが推奨されています。
国公立受験の人に関しての是非は分かりませんが、
私立志望ならこれは必要ありません。
僕自身、世界史の流れなんて意識したことがないです。
そんなことよりも、
「知識を覚えているか」
「多様な出題パターンに対応できるか」
私立はこれだけです。
流れなんて分かっていなくても偏差値70は簡単。
実際の入試でも強力な得点源にできます。
そこに時間を掛けるくらいなら、
偏差値や入試の得点に直結する勉強をしましょう。
仮にそこに3か月程度かかるなら、
その期間でMARCHや早慶で戦える力を付けられる。
折角の独学です。
巷で良く言われて皆がやっているから、ではありません。
自分の利にダイレクトに繋がる学習を意識してください。
ただ、この際1つ注意してほしいことがあります。
「流れを学ぶ勉強をしない」と聞くと、
詰め込みのイメージを持たれるかもしれない。
しかし、それは違います。
これから説明しますが、
詰め込みをするわけではありません。
無理せずとも結果的に、
詰め込まれた状態になっているだけです。
・実学と受験科目の世界史は違うよ?これ知るだけで爆上げ必至⇩
世界史爆上げの起爆剤!実学や教養とは違う単なる「受験科目」として攻略する
・世界史通史最速学習法!あえて流れを掴まない理由とは?⇩
【流れを掴むな】1ヵ月でもデキる世界史通史の最速学習法!どうやって?いつまでに?
偏差値70編:通史問題集のみを使う

世界史の学習となると、
暗記が切り離せませんよね。
特に独学で、しかも先述のように流れは気にしなくて良い。
となると詰め込みをイメージされるのも無理はありません。
確かに暗記は必要です。
しかし詰め込みは必要ありません。
受験世界史でお決まりのパターンがあります。
それは流れを学んだら、
一問一答や用語集を使って、
必要な知識を詰め込むというもの。
これは非常に効率が悪いです。
やらないでください。
流れを掴んだり一問一答や用語集を用いた勉強は、
基本インプットに寄った学習ですよね?
世界史の学習にはインプットだけでなく、
アウトプットの両方が必要になります。
しかし、それぞれに勉強を分けて行う必要はありません。
インプットとアウトプットの両方をいっぺんに行う。
こうすることで時短にも繋がり、早くに成果も得られます。
これを踏まえると、
基礎を固めるには通史問題集だけで十分。
これだけでも河合塾全統記述なら、
偏差値70以上は間違いありません。
そしてMARCHの合格点はおろか、
早慶でもある程度は戦えるようになります。
>>「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・
通史問題集を上手く使えば、
詰め込もうとせずとも、
自然と頭に染み込んでいきます。
それも単なるインプットよりも、
「もっと早く」「確実」にです。
わざわざインプットのためだけの学習。
こんなことをする必要はないんです。
通史問題集から着手する際、
独学だと恐らく初めは何も分かりません。
僕もそうでした。
それでも全くの0から、
通史問題集を使っていきましょう。
使い方次第で自然と無理することなく、
必要な知識が徹底的に身に付きます。
そんな効果的な問題集の使い方が出来るのも、
オリジナリティの高い独学だからこそです。
その利点はMAXで活用しなければ勿体ないですよね。
具体的な勉強法はここでは割愛します。
こちらの記事にまとめているので参照してください。
⇒【独学で攻略】楊貴妃しか知らなかった僕でも1日2時間で偏差値70以上に仕上げた世界史勉強法!
難関大学対策編:世界史の上級者

通史問題集を徹底的に終えたら、
難関大学に向けた準備に入ります。
基本的には通史問題集のみで、
殆どの入試には対応できるようになるはずです。
しかし、あくまで通史の範囲を抜けません。
一部の難関大学では、
それ以上を求められることも珍しくない。
そしてその難易度の高い知識こそが、
私立の世界史の本骨頂なのです。
そこに対応するためには通史問題集よりも深く、
ニッチな所まで手が届くような学習をする必要があります。
そこで使うのが、
テーマ史や「実力をつける100題」などですね。
テーマ史では近現代史のように、
テーマに分けて深堀された問題が扱われます。
100題は通史問題集の難易度を上げて、
厳選された100題の問題から構成されます。
通史問題集が完成されたら、
この辺りをこなせると良いです。
ここまで出来たら世界史の上級者でしょう。
レベル的には私立文系のどこの問題でも、
合格点は取れるようになります。
ただこれには注意点であったり、
全員が解くべきという訳ではなかったりします。
その辺はこちらの記事で説明しています。
宜しければご覧ください。
⇒【世界史】通史が終わったら何をする!?状況に合わせた今後の流れが分かります!
過去問編:志望校での合格点が約束される

ここまで出来れば学力的にはもう十分でしょう。
その上で、万全を期するために過去問をやります。
過去問を使う目的は力試しではありません。
「既に出来上がっている力を更に高めるための材料」
こういう目的で使いましょう。
過去問では問題集だけでは触れる事の出来ない、
難しい問題も多々出てくると思います。
それは知らない知識という意味だけではありません。
知識自体は知っているものでも、
「こんな風に出題されるんだ」、
ということに気付くこともあると思います。
このような気付きこそが過去問を解く意義です。
過去問を解く。
そこで失点すること、
復習することで自分の穴が見つかります。
そして、その穴を埋めていく。
そういう勉強をしていく。
これらの作業を繰り返します。
ここを徹底することで、
合格点を約束されるほど、
世界史力が完成されていきます。
なので過去問を解くこと自体よりも、
復習に力を入れるくらいの意識で丁度良いです。
未知だった知識や誤答した問題は、
二度と間違えないように仕上げてください。
1つ補足があります。
志望校の過去問を解くのは勿論ですが、
志望校以外の過去問も解けると理想です。
僕は慶應志望でしたが、
早稲田の過去問も解きまくりました。
僕が教えている人もそうしています。
受験はせずとも志望校と、
同じようなレベルの過去問を解く。
そこには様々なメリットがあります。
この効果・メリットについては、
こちらの記事をご覧ください。
最後の詰め編:世界史が絶対に得点源になる

原則過去問までしっかりこなせれば十分です。
しかし過去問を解いた先にある、
この作業がしっかりできれば、
合格点どころか得点源になる事は間違いなし。
ここでやるべき作業とは、
過去問で課題を見つけた埋め合わせていくこと。
これは過去問の復習とは別物です。
過去問を解いていると自分の弱点や、
ここを補強したら更に得点が伸びる、
というのが分かってきます。
例えば僕で言うと慶應法が第一志望でした。
「頻度の低い用語を問われることが多々ある」
過去問を通じてこう感じたので、
用語集の頻度の低い用語に絞って、
集中的に覚えたりしていました。
このように過去問の演習を通じて、
得点に直結するであろうと感じた対策を講じる。
これが最後の詰めです。
⇒用語集使うべき人とそうでない人!あなたはどっち?慶應法が使い方まで解説
最後の詰めとして何をするかは人によって異なります。
そのため自分の弱点や志望校の性質を、
しっかり分析することが大前提です。
ダイレクトに得点アップに寄与する。
そういう策を打てるようにしてください。
ここまで出来たら十中八九で、
実際の入試でも得点源になっているでしょう。
さいごに
独学なんて超簡単
私立の世界史の独学は、
難しい事なんて全くありません。
学習自体は非常に簡単です。
(日本史でも同じ)
”自分が何をどんな流れで勉強すべきかを考えるのが苦手”
強いて言うなら、
そんな人には難しく感じるかもしれませんね。
でも今回お伝えしたことで分かったと思います。
やる事は非常に明快です。
「問題集を解いて過去問を解く」
「詰めでピンポイントな補強をする」
シンプルに言うとこれだけです。
それ以外は必要ありません。
それぞれのやり方については、
これまでに張ってきた記事を参照してください。
その通りに進めてもらえれば大丈夫です。
成果はすぐに表れると思います。
あまり難しく考えずに是非独学にトライしてみて下さい。
⇒【私立世界史】ノートにまとめるのは無駄!私立世界史の特徴に合わせた勉強はこちら
⇒「ヤバい!世界史が覚えられない」私立志望限定のウソみたいに早く伸ばす方法とは?
⇒【痒い所にも手が届く】早慶志望はいつから・どうやって世界史を勉強すべき?





