
志望校合格への目安として、
最も参考となる指標。
それは過去問です。
模試じゃありません。
志望校の受験者層のレベルは、
毎年ある程度一定になります。
合格最低点と照らし合わせると、
自分の立ち位置がハッキリ分かる。
⇒【決着】絶対こっち!模試OR過去問どっちを信用するべきか?
じゃあその過去問はいつから解くべきか?
過去問を解き始めるタイミング。
その正解を一つに断定するのは難しいです。
人それぞれ学習進捗が異なるため、
各人毎に解き始めるべきタイミングも異なります。
各人がどんな状況にいるのかを加味しながら、
過去問を開始するタイミングを考える必要がある。
過去問を解き始めるべきタイミング。
今回は場合分けしながら、
これを説明します。
あなたの最適なタイミングを、
そしてその際の注意事項を、
掴んでいってください。
過去問を解き始めた方が良いタイミング
【前提】学習進捗次第感は否めない

受験生それぞれ勉強の進捗は異なりますよね?
学力が成熟して早々に志望校合格水準の人。
勉強の取り掛かりが遅く基礎も出来ていない人。
こういう進捗は人それぞれです。
勉強の仕上がりに応じて、
スケジュールや進め方は、
当然変わってきます。
偏差値80の人と偏差値40の人。
やる事も全く違いますし、
同じスケジュールで勉強するほうが、
寧ろ不自然じゃないでしょうか?
これと同様に「いつから過去問解くべき」、
に対する答えを断定するのは難しいものがある。
従って自分の置かれている立ち位置と、
照らし合わせて考えることが前提になります。
このことは覚えておいてください。
以降では大まかにそれぞれの立ち位置を、
上位層・中間層・下位層に分けて考えます。
そのボリュームで言えば、
2:6:2くらいでイメージしてください。
上位層:このままいけば合格が妥当な受験生
下位層:基礎も固まっていない逆転合格狙うような人
中間層:上位層と下位層以外の広い幅に該当するボーダーライン~少し下くらいの人
こんなイメージを持ってもらえると、
この先が頭に入りやすいと思います
では見ていきます。
上位層は早ければ早い方が良い

順当にいけば合格が妥当な上位層の人。
過去問を解き始めるタイミングは、
早ければ早い方が良いです。
既に勉強が順調に進んでいるはず。
自分と志望校の残りの距離を早くに把握し、
その分析と対策を行って、
距離を着実に詰めていけばゲームクリアです。
この作業をするに当たり早くに過去問を解けば、
それだけ多くの時間を確保できます。
過去問を解き始める時期次第では、
自分と志望校の距離を詰めるだけでなく、
100回受けて100回受かる位にまで、
仕上げることも可能でしょう。
上位層の人に関しては、
具体的にいつからというのはないです。
この人たちには過去問を解き始めるのが、
早すぎるなんてことはありません。
まだ解いてないなら今すぐに解きましょう。
早ければ早いほど良く、
万全を期して受験に臨めます。
中間層は可能なら〇月には解き始めたい
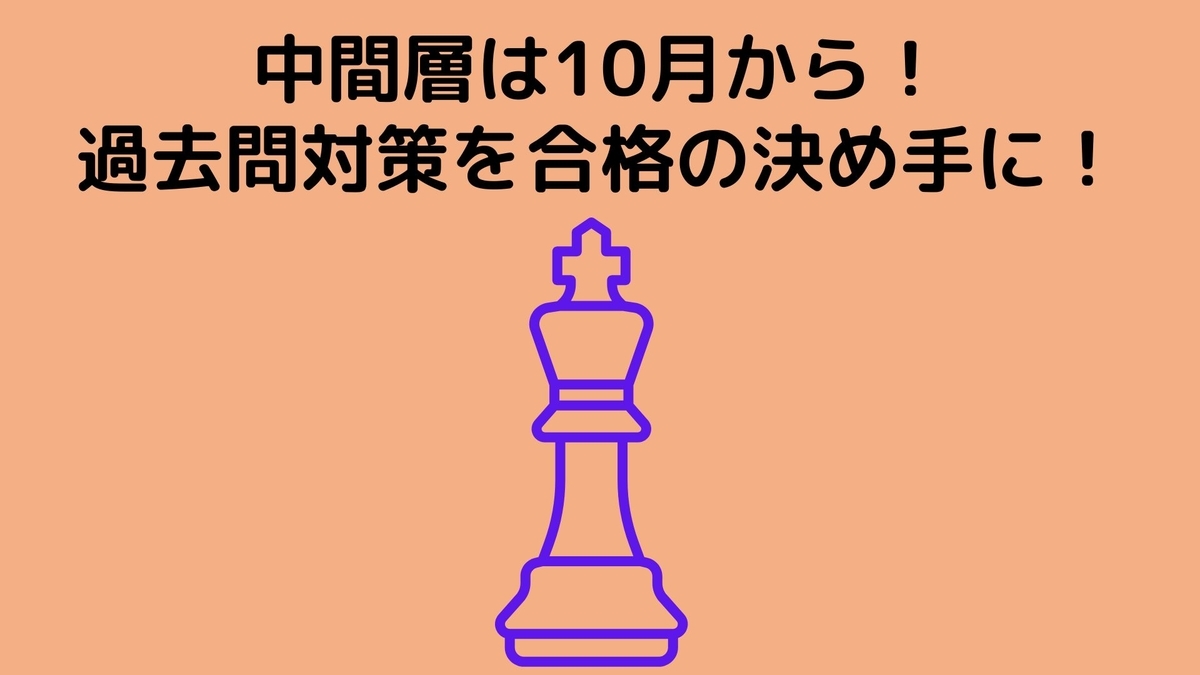
志望校の志願者大多数に含まれる中間層の人。
この人たちはボーダーライン、
もしくはその少し下にいます。
このタイプは志望校に対する基礎学力と、
過去問対策による効果のバランスを、
上手く取る必要があります。
過去問対策だけ早くにやっても、
そこそこ基礎学力が無ければ、
自分と志望校の距離も測れません。
そうなると過去問の対策を行っても、
効果が限りなく薄くなります。
基礎学力も高めつつ良き塩梅で、
過去問も解き始めて、
万全を期すといったところです。
可能であれば10月くらいから、
徐々に着手するのが良いでしょう。
この層の人たちは過去問対策が、
合格の決め手になることも多々あります。
以下の要領でこなすためにも、
時間にはゆとりを持って考えるべきです。
まず過去問では繰り返し解くことが重要です。
特に第一志望のは最終的には10年分を、
満点にするくらいの気持ちでやると良いです。
また過去問を解くと同時に自分の課題を見つけ、
それに対する補填策を打って行かなければいけません。
つまり、こういうイメージですね⇩
・第一志望のは10年分解く
・満点取れるくらいに繰り返す
・過去問の分析を行い、その傾向に合わせた対応策を講じる
これらを行うに当たり
最低限の十分な時間を取るためには、
いつから始めるべきか。
そういう考え方になる。
10年分解くだけなら、
1ヵ月も掛からずにできると思います。
でも徹底的に繰り返したり、
講じた対策の成果が出るまでには、
もう少し時間を見た方が良い。
勉強というのは即効性が低いです。
解く順番変える・時間配分を工夫するなどは、
スグに成果に現れるかもしれません。
しかし根本的な学力に関わる部分は、
どうしても時間が掛かります。
3ヶ月あれば最低限十分な時間を確保できる。
そう考えておくと無難です。
少し余裕を持って10月くらいから、
解き始めると良いと思います。
下位層は注意は必要
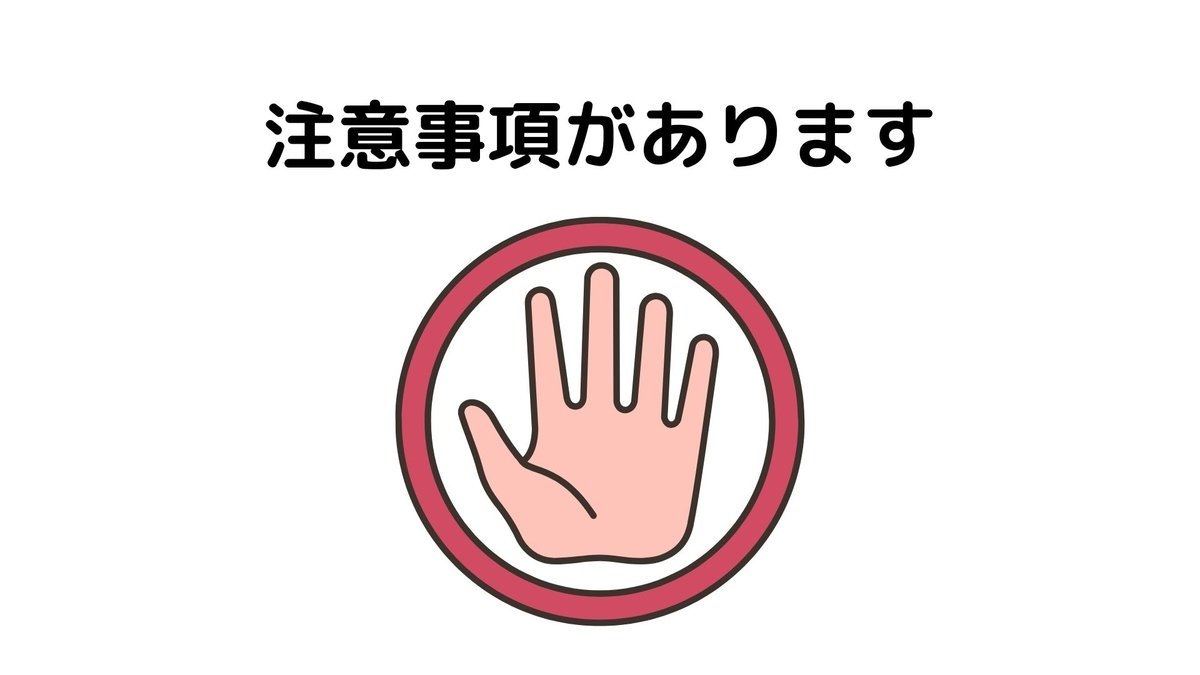
ここでは下位層の人たちに関してです。
現状合格争いに入る余地もない圏外。
逆転合格狙うような人たちです。
この人たちは以下の点に、
注意しなければなりません。
・合格に求められる必要な基礎学力が無い内は過去問は時期尚早
・とはいえ、遅くともいつ頃からは過去問を解くというのは自分の進捗を加味して決めておく
この下位層タイプの人は、
合格に求められる基礎学力がない。
これは過去問対策以前の話です。
過去問対策はベースがそこそこあって、
初めて意味を成します。
何が分からないのか分からない。
復習しようにも復習にならない。
これじゃ得られることがありません。
勝負の土俵に立てていないということ。
必要な基礎学力が無い段階では、
過去問は圧倒的に時期尚早です。
過去問を活用する理由は、
志望校との距離感を知り対策を行うこと。
これができる状態にないなら、
早めに解いてもあまり意味はないでしょう。
極端な話し高校入学直後に、
志望校の過去問を解いたって仕方ありません。
何も分かりませんよね?
自分と志望校に距離があり過ぎる時は、
過去問やっても意味が無いってことですね。
何も分からないということが分かるだけです。
早ければ良いってものじゃありません。
その人に合ったタイミングがあります。
人によっては何も分からないことが分かれば、
危機感を感じて勉強すると考える人もいるかもしれません。
個人的には危機感を感じるのも一長一短。
気持ちだけ急いて地に足つかなくなる。
こうなったら本末転倒ですから。
本来踏むべきステップを飛ばした結果、
気持ちだけ焦って遠回りになりかねません。
それなら別に無理に過去問やらずに、
地に足着けて進むほうが良いはず。
上を見すぎると足元が脆くなる恐れはある。
ただ一理はあるとは思います。
冷静に自分を把握して、
きちんと地に足ついてやれるなら、
全く問題ないですし。
解くにしても赤本の一番古い年度を、
1年分解くくらいに抑えましょう。
後々に力が付いて過去問対策を行えるよう、
無駄な過去問消費は避けたいです。
それに1年分解けば、
何も分からないということは分かると思います。
話を戻します。
過去問を解く時期を遅らせることも、
時に必要という話でしたね。
しかしいつ解き始めるのかは、
予め決めておいた方が良いです。
基礎学力が出来てから解くというのは、
それがいつになるのか不明瞭ですよね?
基礎が出来てから~とか言ってたら、
いつまでも仕上がることなく、
受験を迎えるかもしれません。
自分の学習進捗を加味しながら、
遅くともいつ頃には解き始める。
こういうことは設定しておきましょう。
下位層である場合は志望校で求められる、
基礎学力の向上が何よりも急務です。
それが無いと、
いくら過去問だけやっても、
合格できないから。
しかし過去問をやる時間も、
当然確保すべきです。
いつ頃には過去問を始めると明確に決めて、
そこまでに基礎学力を仕上げるように、
計画的に取り組みましょう。
そうでないとその勉強をダラダラと続けて、
過去問やる時間を確保できなくなってしまいます。
これは最悪です。
しかし厳密には過去問をやるタイミングは、
以下2点によって異なります。
- どれほど基礎学力が欠如してるか
- どれくらい時間が残されているか
これらを考慮しながら、
いつまでに過去問に入れるようにするか。
そのためにどういうペースで、
必要な勉強を仕上げていくか。
自分の状況を分析し、
適切な期限を決め、
間に合うように勉強を進めましょう。
※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!
さいごに
上手く過去問を使おう
さて、如何でしたか?
過去問を開始すべきタイミング。
これは各人の学習進捗等によって異なります。
早くに始めた方が良いのは分かっていても、
理想と現実の折り合いをつけなきゃいけない。
過去問はいつ開始すべきかだけではなく、
その使い方も大事になります。
最善のタイミングと最善の使い方。
これが出来れば非常に強い武器となるでしょう。
その辺は以下の記事で説明しています。
併せてご覧ください⇩
【攻略】志望校合格への決定打!ライバルに差を付ける赤本120%フル活用法を解説!




