模試でA判定取れるよう勉強することが志望校合格に繋がる
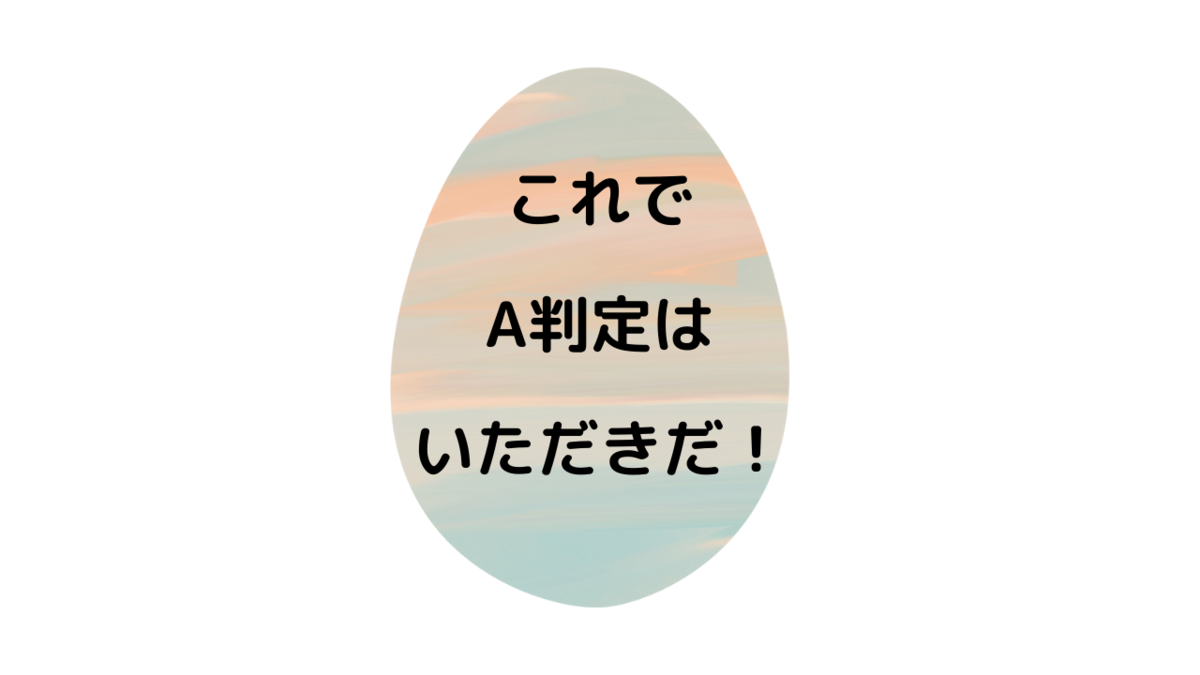
みなさん模試は受けますよね?
模試受ければ成績に応じた自分と志望校との距離感が掴むことができます。
その判定は自分の立ち位置を知るには十分な材料となるはずです。
どうせ模試を受けるならA判定欲しくないすか?
A判定取れるってことは、その時点での学力が志望校に対して劣っていないということになります。
それは自信にも繋がるだろうし、そのまま勉強続ければ高い確率で志望校に合格できるってことになります。
「そんなん言ってもA判定なんて簡単じゃないよ」と思うかもしれませんね。
志望校のレベルが高いほどそう思うかもしれません。
でも、A判定取るための、模試に向けた勉強の仕方があるとしたらどうですか?
もちろん受験勉強は模試が目的ではなく、その先の合格が目標です。
しかしA判定を取れるという事は、学力的に志望校合格にも着実に近づいているという事実は否定することが出来ないと思います。
特に難しい事を知ろという訳ではありません。
模試の過去問解けー!なんて絶対言いません。それじゃ勉強の目的が模試になっているので意味が有りません。あくまで志望校合格のための勉強をすべきで、模試はその過程に過ぎません。
ただ、模試を上手く利用して、模試に向けて普段の勉強に少し工夫をするだけで面白いように成績は伸びます。
根拠は僕自身です。英検3級の英語力に知識0の世界史から勉強開始2か月で慶應法のA判定を出しました。(駿台全国模試)
今回は、そんな模試に向けた勉強法についてお話ししましょう。
※お分かりと思いますがA判定取れば=合格ということではありません。
A判定というのは志望校合格への道のりにあるに過ぎません。A判定取ってそこで満足してしまうと落ちる事も不思議ではないので注意してください。
模試に向けた勉強法の全て
step1 模試までにすべきことに目途を立てよう
まずはざっくり大まかな考え方を示すので、↓の枠の中を読んでください。
それぞれの詳しい内容はこれから説明していきます。
めっちゃシンプルなので、この記事読み終えたらすぐに実践可能です。
模試でA判定を取るということは、当然ですがA判定を取れるだけの学力があるということですね?
受ける模試での志望校の偏差値はネットで調べればすぐに出ると思います。
つまり、そこに相当する力を限られた期間の中で身に着けようということです。
たとえば偏差値70でA判定が出るなら、その模試の偏差値70は何点くらいとれば良いのか調べるなり考えるなりします。
そこに必要な点数が分かれば、模試の試験レベルや試験範囲などと照らし合わせた上でざっくりと自分が何をどれくらいできなきゃいけないのかということに目途を立てることができるでしょう。
たとえば文法なら~くらいは完璧にならないとなとか、社会なら○○~△△までの範囲は問題集完璧にできるようになりたいなとかですね。
勿論これらを完璧に把握することは出来ないのでザックリとで構いません。少々厳しめというか、自分にとって負担が掛かるくらいの目途を立てる事をお勧めします。
step2 立てた目途を日割りにして着実に取り組もう
ザックリと目途を立てたら、それらを全て完璧に行えばA判定は取れるだろうということになりますよね。そうでないなら見立てが誤っているということになります。
でも、目途を立てても自分で決めたやるべき内容を全て完璧にこなすって案外難しいと思うんです。
そんなに順調に進むなら誰も勉強苦労しないし、みんな高得点取れるということになりますからね。
じゃあ何を工夫したらよいでしょうか?
自分で決めたやるべき全内容を、日割りにしてみて下さい。
例えば100ページを10日で終えようとしたら1日10ページになりますよね?
考え方はこれと同じです。
やるべき量はどれくらいあるのか、何周するのかなどによっても、やるべき総量は変わってきます。この総量を残された日数で割れば、1日のやるべき量=to doは自ずと決まってきます。
その定められたto doを日々こなしていけば、最終的にはやるべき全てを満たす事になるはずですよね?めっちゃ簡単じゃないですか?
不測の事態や、休息日もあるとは思うので、そこは個人の裁量で加えながらで結構です。
でも、何でこのような勉強法が有効なんでしょうか?
その理由についてみていきましょう。
何故この勉強法をすべきか?
近くに目安や目標を置く方が無駄もなく勉強を効率的に進めることができるからです。
例えば、志望校を基準にやるべきことを考えるとしましょう。
既に11月とかで残り3か月ほどであれば、何をすべきかも適切に考えられると思います。
しかし残り半年、ましてやそれ以上の期間があるとしたら、その長い期間の中で正確に自分がやるべきことを選定するのは難しいです。
その時々の学力次第でやるべきことは変わるし、期間が長すぎるとあれも出来る、これもしたいなど本当に自分がやるべきことが見極めにくくなってしまいます。
また、それだけ長い期間があると緊張感を維持するのが難しく中だるみ期間ができる恐れもあります。
一方で模試は、勉強の進捗管理の基準に適しています。
受ける回数を自分で決める事も出来るし、比較的短い間隔で受験することができます。
それくらいの短い期間であれば次の模試を目安にして、その時までに自分が何をすべきかも見極めやすいし、その期間で自分ができるキャパも自分で測れると思うので、あれもこれもと手を出さずに本当にやるべきことに絞る事が可能になります。
つまり、結果的にはその短期間で最大限に学力を上げるための最も効率の良い勉強法になるということです。
そして、次の模試でA判定という明確な目標があり、やるべきことがびっちり決まっている状態なら緊張の糸は切れにくいはずです。
なぜなら緊張の糸が切れたら、日割りで決めたやるべきことを全て終わらせることが出来ないからですね。
じゃあ、短期間でとは言うけれども、どれくらいの頻度で何回くらい模試を受けたら良いのでしょうか?
この点について説明していきます。
模試の受験回数は制限しよう
さて、先ほど受験よりも模試の方が身近な目標、目安として優れていて勉強が進めやすいという話をしました。
しかし、だからと言ってでたらめに何でも受ければいいとはなりません。
勉強には成果が出るまでの時差が存在します。
数週間~1か月では中々その成果は出ず、恐らく実感としても湧きにくいと思います。
そのため、超頻繁に受けるというのはあまりお勧めできません。
それよりも2~3か月という期間を置いて、その期間に着実にやるべきことを終え確実にA判定を出す意識を持つ方が遥かに上手くいくでしょう。
その期間を踏まえると、私立受験の人は年間3回くらいで良いと思います。
メジャーな模試を期間置いて受けて確実にA判定を狙いましょう。
私立文系の人が受けるべき模試、その基準はこちらから↓
国立志望の人はマーク式と記述模試両方受ける事になると思いますので3回では収まらないと思いますが、それぞれメジャーなものだけ最小限で受け、+オープン系の模試を受ければ十分すぎると思います。
模試への準備の積み重ねが志望校合格に繋がる
さいごに
如何だったでしょうか?
模試を目安に勉強を行うことで効率的に学力を伸ばすことができます。
そして、その学力向上は間違いなく志望校にも生きてくるでしょう。
A判定を一度取れば、今後の更なるモチベーションにもなります。
模試1つ1つを軽率にせず、しっかり向き合って勉強を勧めましょう。
ちなみに模試は受けるだけじゃ意味が有りません。復習は絶対に行うようにしましょう。模試後の復習に関してはこちらから↓

