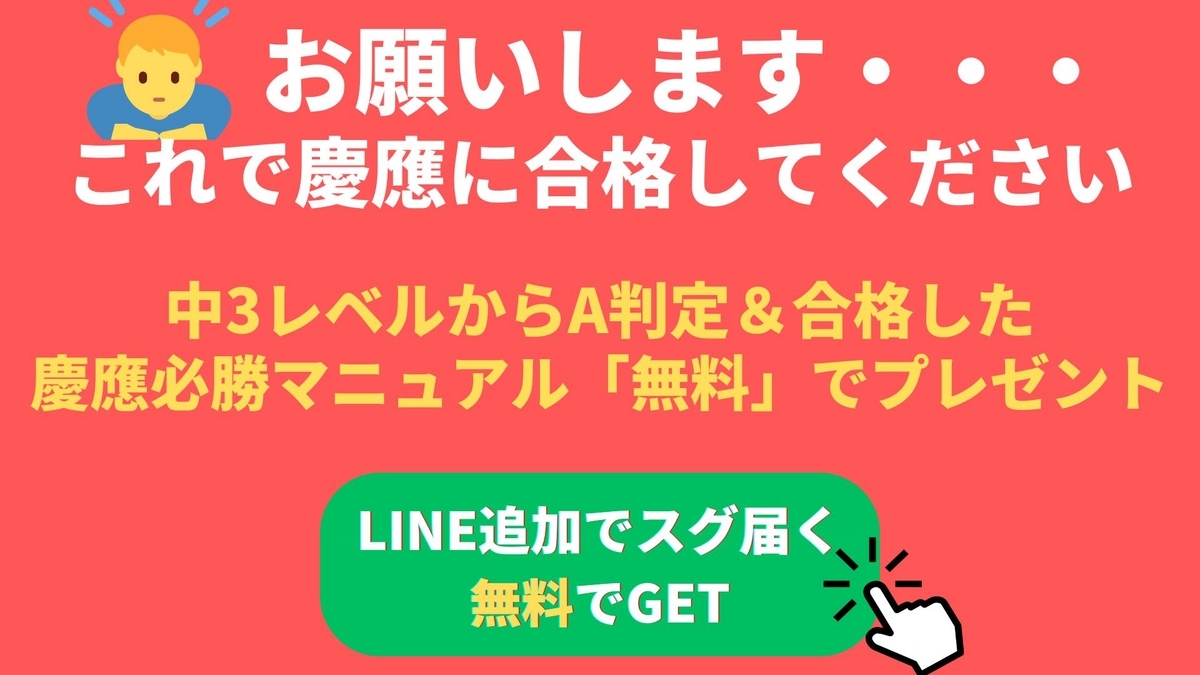模試でA判定でも落ちたらそれは必然
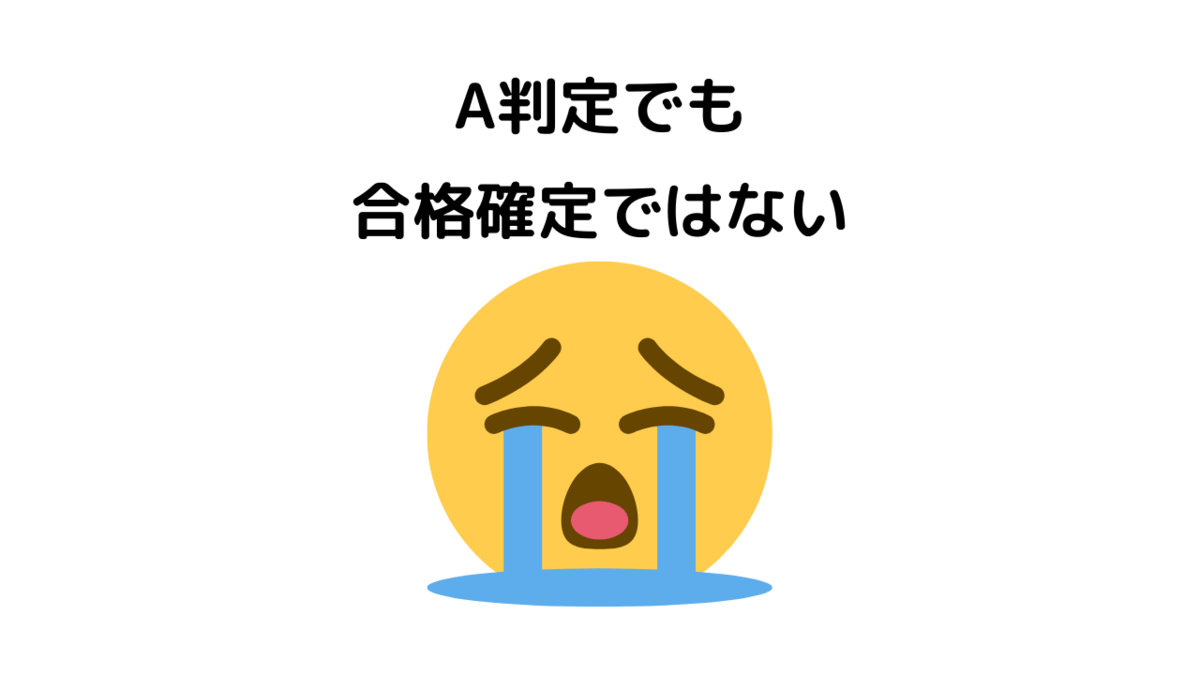
「わーい、模試でA判定だ!これで落ちる訳ないぜぇグフフwww」
「なんてったって模試のA判定とは合格率80%以上だもんね!」
本当に?
A判定なら落ちないの?
A判定だから受かるとは、
必ずしも言い切ることは出来ません。
A判定でも落ちる事はザラにあります。
模試の判定は絶対じゃない。
A判定だけど落ちるという人もいます。
逆にE判定から受かる人もいます。
「模試の判定は信用するな」
現状はそう聞こえてるかもしれませんね。
けど、それは違う。
A判定であるに越したことは無いです。
寧ろA判定を積極的に目指すべき、
とすら考えています。
「E判定でも気にすることは無いさぁ」
こんなこと軽々しく言うつもりもない。
志望校の合格には、
模試の判定が全てではないというだけ。
そもそもの模試の捉え方。
A判定なのに落ちる原因とその対処法。
今回はこの辺についてお話しします。
模試判定の捉え方
歯磨きしても虫歯になる事はあるから歯磨きしないよ、とはならない
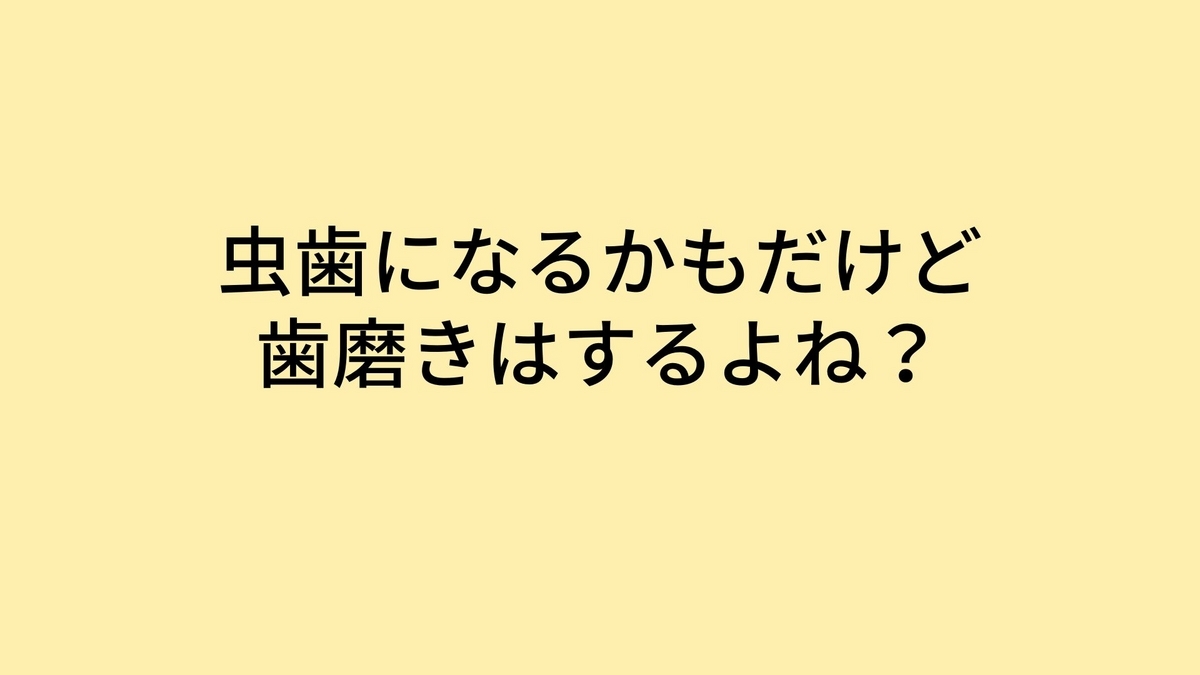
この記事の本旨は、
「A判定でも落ちる事はあるよ!」という話。
でも冒頭の通り、
A判定を目指さなくて良い、
ということにはなりません。
A判定が出る。
これは素晴らしい事です。
少なくとも模試を受けた時点では、
他の志望学生よりも相対的には良い位置にいます。
学力的には順調であることには間違いない。
模試の判定は言ってみれば、
指標のようなものです。
より優れた判定ほど志望校に対して、
近い位置にいると思ってください。
であればA判定が取れるよう、
勉強を積み重ねていく。
それは志望校に近づいている、
と言うことができます。
A判定でも落ちる事はある。
だからと言って、
A判定を目指さない、
取れなくて良い理由にはならないはず。
「歯磨きしても虫歯になることはあるから歯磨きはしないよ」
これくらい極端すぎる、
最早暴論のような考え方です。
だからこそ模試の判定には、
拘りを持って良い判定を目指すべき。
と、まあここまでは前置き。
大前提となる考え方ですね。
ここからはA判定でも落ちる件について、
話を深掘りして行きます。
A判定だからと言って合格が保証されている訳ではない。
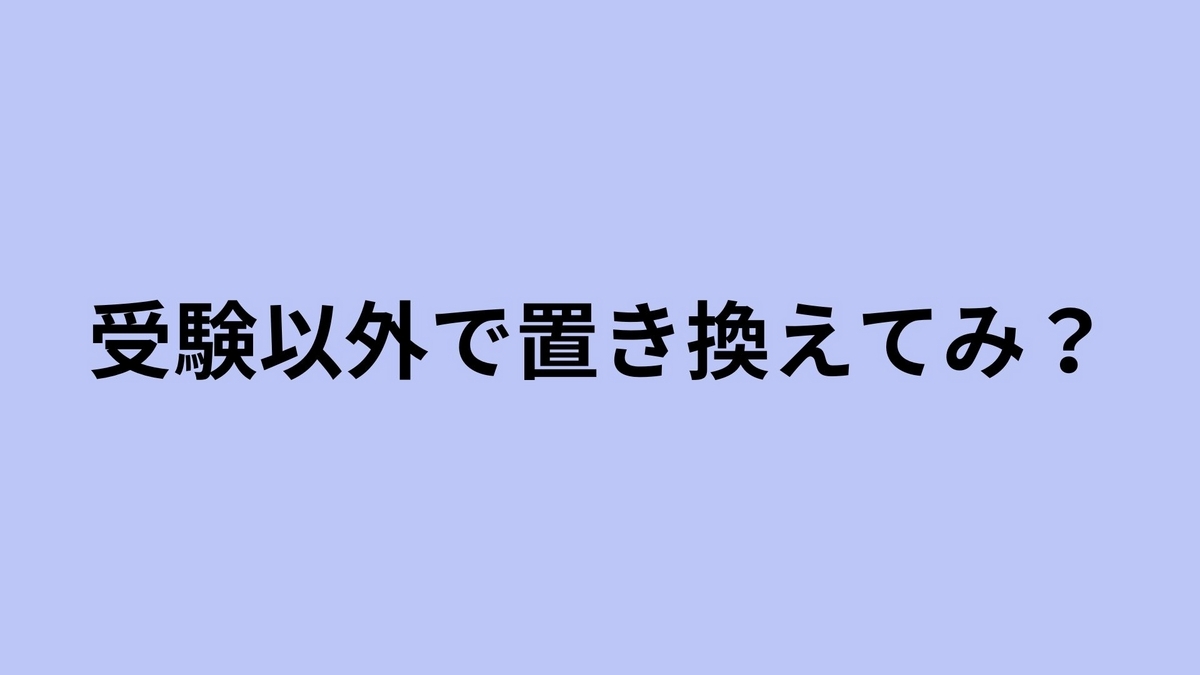 そもそも模試は模試。
そもそも模試は模試。
そして受験は受験です。
練習では出来たけど、
本番は出来なかった。
練習試合では負けたことも無い相手。
だけど公式戦では負けてしまった。
こんな経験したことないですか?
たとえそれが10回に1回だとしても・・・
結果は結果です。
そうなってしまう理由は様々ですよね。
緊張して力が発揮できなかった。
普段しないミスが本番で出てしまった。
などなど。
受験とは一つの大きな出来事です。
定期試験なんかとは重みが違う。
だからこそA判定で落ちる事に不可解な、
やるせない気持ちになるのでしょう。
でも他の事に置き換えてみれば。
絶対にないという話ではありません。
とは言っても受験と模試判定の関係において、
A判定で落ちる原因はある程度特定できます。
僕自身の受験の経験や、
これまで見てきた多くの人から、
色々と学ばせてもらいました。
なんでA判定なのに落ちてしまうのか?
下段以降で探っていきましょう。
A判定でも落ちる原因5つと対処法~落ちるのは必然だ
勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議な負けなし
A判定から受験に落ちる。
その原因というのは一つではありません。
人によってその原因は異なるのが自然です。
主に考えられうる原因を、
5つ挙げてみました。
どれか一つでも当てはまれば、
余裕で落ちる事はあります。
そして挙げている5つというのは、
決して偶然起きたものではありません。
起きるべくして起きた必然ということです。
プロ野球の名監督である、
故・野村克也氏はこう述べています。
勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし
これは受験にも当てはまる事です。
なんか分からないけど上手くいって、
実力以上の学校に受かる事もあります。
これはマグレ・奇跡と呼ぶべき現象です。
(運も実力ではあるので合格自体は誇るべき)
一方どんな理由であれA判定から落ちる。
ここには必然的な理由があります。
失敗に偶然は無いということです。
では、一つずつ説明していきます。
・偶然模試の出来が良く実力以上が出てた
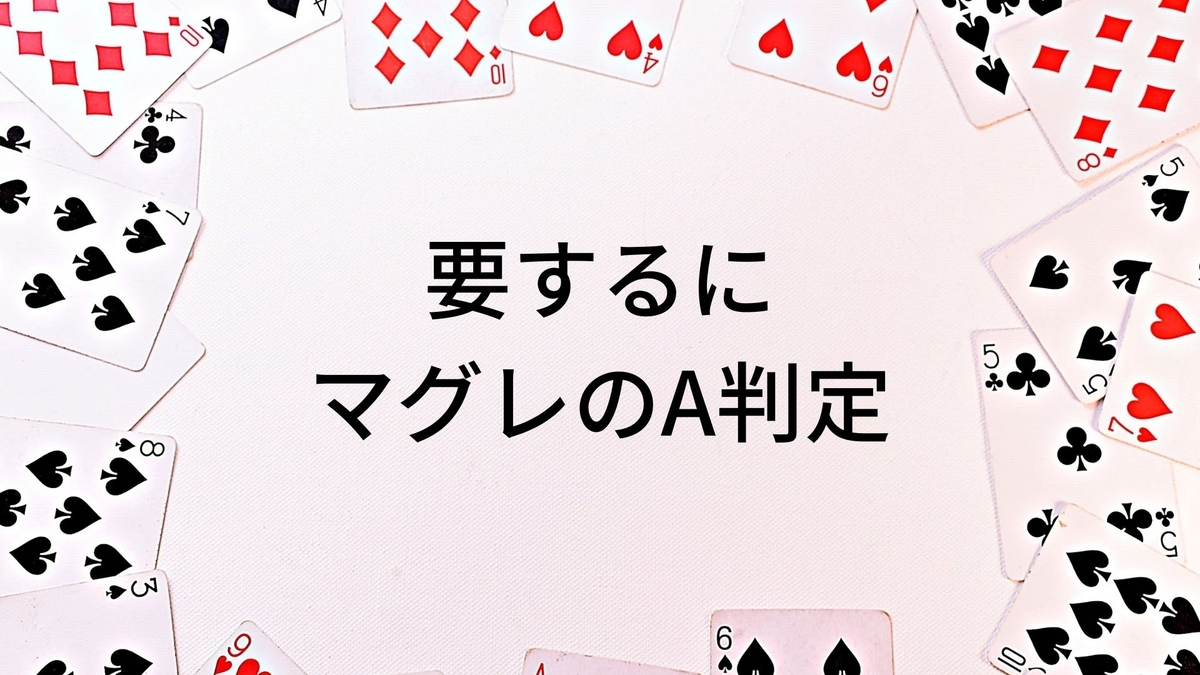 模試でも受験でも、
模試でも受験でも、
その瞬間の一発勝負です。
マグレパンチというのは起きるもの。
先述した通り勝ちに不思議の勝ちありと同様、
マグレで良い結果が出てしまうこともあります。
例えば得意な問題ばかりが、
偶然出てくるとかそうですよね。
運も実力ではあります。
その模試ではツキが味方した、
ということでしょう。
でも、これは本来の実力ではありません。
いくら模試の判定が良かったからと言って、
それが時の運であるなら、
実力相応の力では受からない。
常にA判定が出ていること。
その時一回だけA判定が出た。
この2つは意味合いが全く違います。
偶然のA判定であれば、
その結果自体は喜ばしい事です。
しかし受験でも運が味方するかは分かりません。
自分を客観的に見ながら邁進しましょう。
そして運が味方することなくとも、
合格を掴み取れるようにならなければいけません。
※追加後スグにあなたのラインにPDFが届きます!
・模試の判定に過信して油断があった
 「A判定出た!これで受かるわ!」
「A判定出た!これで受かるわ!」
なんて思えば当然気が抜けますよね。
過度にその判定を信用してしまう。
そして以降の勉強の手を抜けば、
それは落ちるに決まっています。
そもそも模試判定というのは、
模試を受けた時の相対的な学力です。
そして模試の返却には、
時間差がありますよね?
模試が返却されるのは多くの場合、
一か月~二か月掛かります。
その判定は一か月~二か月前のあなたの実力。
今やったらどうなるかは分かりません。
ましてや受験が数か月後ならば、
その間にも学力に差は付きます。
判定に過信して手を抜けば、
他の受験生に追い抜かれる可能性も、
大いに考えられます。
これは特に浪人生にはあるあるかもしれません。
浪人生は現役生よりも、
勉強環境が優れています。
秋くらいまでは模試の成績が優れている。
そういうことが多いです。
ここで慢心して最後には、
「なぜか受からなかった」と、
泣く人が沢山出てくる。
A判定が出ているということは、
それまでの勉強は概ね正しかったってこと。
学力的に他の受験生よりも、
優れている事にはなります。
慢心せず勉強を続ければ、
合格の見込みは大いにある。
過信しないようにしましょう。
・学力的には十分だったけど志望校の個別対策が十分でなかった
 これは簡単に言えば舐めていた、
これは簡単に言えば舐めていた、
ということになるんでしょうか。
模試で高偏差値を取る。
志望校で良い判定を取る。
これらは基本的な学力が、
及第点であることを意味します。
しかし入試にはその入試に特有な傾向、
そして出題形式がありますね。
その他諸々と模試だけでは、
測り切れない要素が絡んできます。
そのために受験生は、
過去問対策をするわけです。
極端な話、試験内容異なるでしょってこと。
なので模試の判定だけでは、
入試合格の十分条件にはなりえない。
例えば国立トップレベルに受かる人でも、
慶應法学部落ちるということはあります。
それは学力的に慶應法学部に劣るからではありません。
慶應法学部が国立とはかけ離れた、
バチバチの私立っぽい試験だからです。
一方で国立組は慶應経済の方が受かりやすい、
とされているのは慶應経済の試験内容が、
比較的国立に近く対応が容易だから。
学力では慶應より上の、
国立トップレベルの受験生。
なのに慶應法に落ちるのは、
傾向や求められることが違って、
対策をあまりしなかったりするから。
これは模試の判定が良くても、
志望校の個別対策不足で落ちるのと、
理屈的には同じことです。
学力は十分でも、
対策不足なら落ちる。
ここに不思議はありません。
学力的に十分。
これだけでは足りないことがあります。
しっかり過去問解いて対策しましょう。
・赤本120%活用法はこちら⇩
【攻略】志望校合格への決定打!ライバルに差を付ける赤本120%フル活用法を解説!
・10回に1回の不合格を引いてしまった
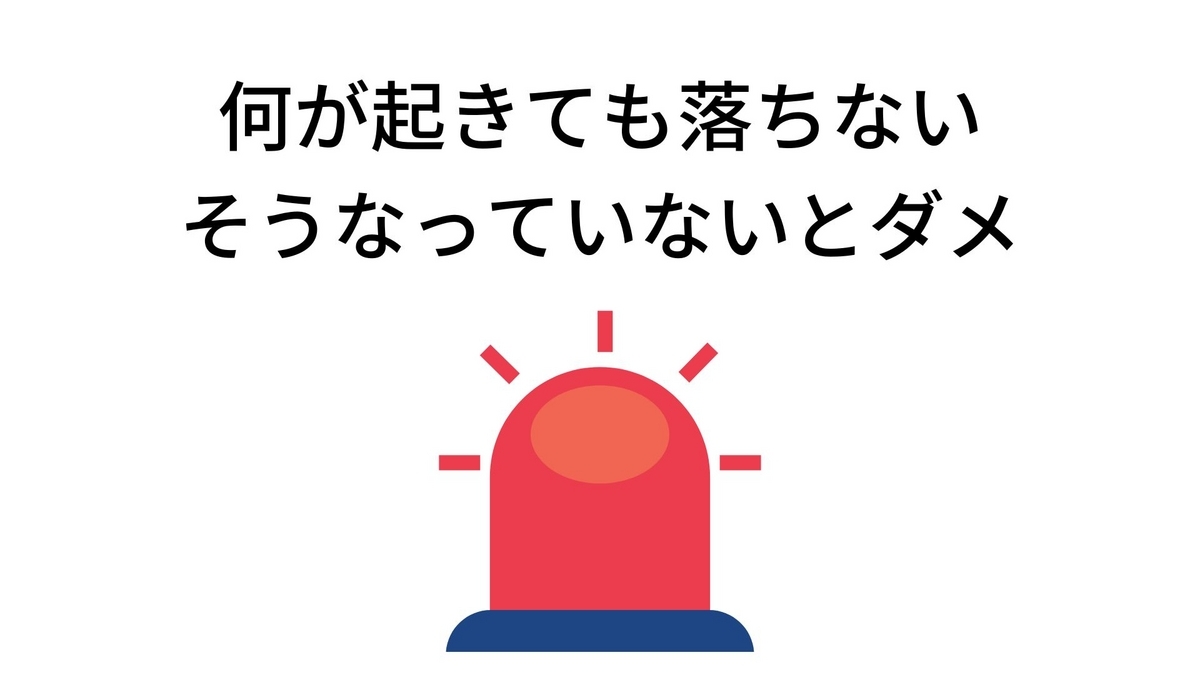
実力が発揮できなかったわけではなく、
当日は持てる力を出したけど及ばなかった。
まあ、ありますよね。
難化したわけではないのに、
普段より解きにくい感じがしたり、
上手くいかない現象。
過去問ではそんなことなかったのに、
受験当日で10回の内の1回を引いてしまう。
これもA判定だったのに、
落ちてしまうケースの一つです。
人によっては、
「時の運」と表現するかもしれません。
けど厳しい事を言うと、
それは偶然ではなく必然です。
「時の運」ではなく、
落ちるべくして落ちた。
単に実力不足だっただけ。
難化した訳でもない。
自分の力が出せなかった訳でもない。
それなのに十分に解けなかった、
ということは・・・
その問題を解く力がなかった。
そう考える他ありません。
10回の内の1回がそこで出てしまう。
確かにこれは残念だと思います
それを招いたのは、
自分自身の取り組みです。
その1回すら生み出さないように、
勉強しなかったからそうなった。
100回受けて100回受かる。
そういう準備をしなかったのが悪い。
詰めが甘かったのか、
漏れがあったのかは分かりません。
一分の隙も無いという状態まで持っていく。
それが出来なかった自分自身の問題です。
常に最悪の事態を想定する。
何が起きても。
難化しても。
体調が悪くても。
それでも余裕で合格できるレベルにまで持って行く。
このような意識を持って、
最後まで取り組みましょう。
ここまででお気付きかもしれませんね。
当たり前のように毎回A判定を出せないなら、
それは明らかな実力不足です。
その次元を超えて初めて、
議論の土俵に立っているものと捉えて下さい。
>>「え、まだ慶應A判定出てないの?」1~2か月ありゃ誰でも取れるのに・・・
・緊張して普段しないミスをしたり力が発揮しきれなかった
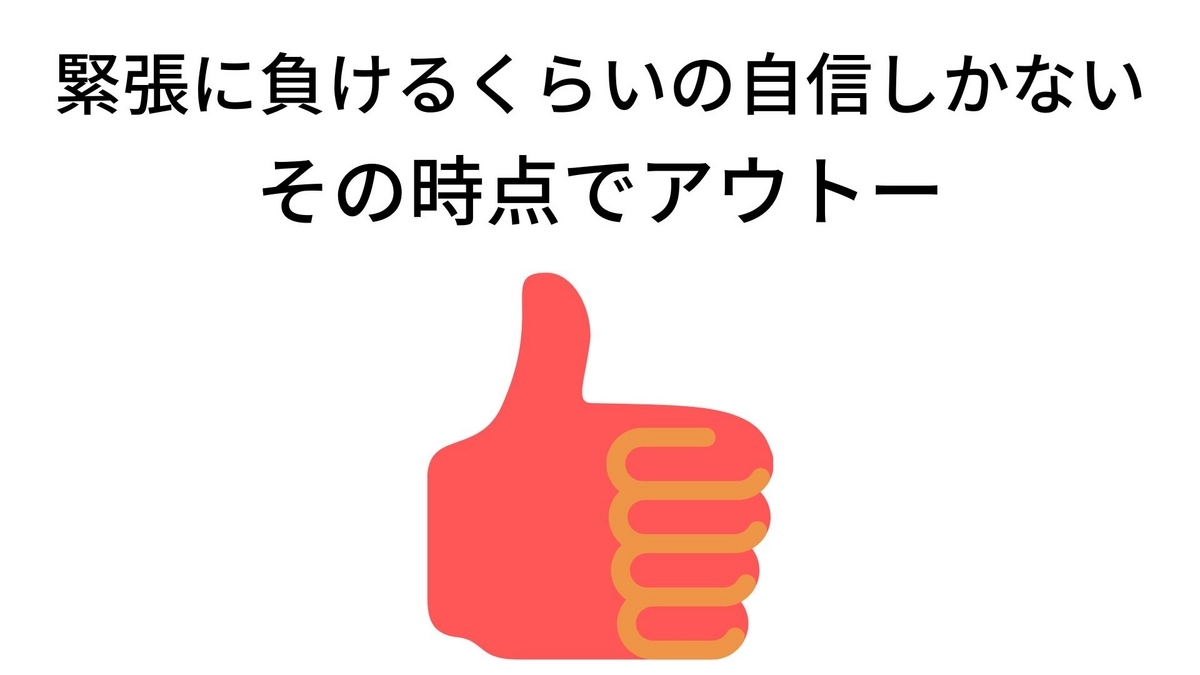
たしかに本番に弱い人っていますよね。
緊張して思うように解けなかったり、
思わぬミスが出ちゃったりと。
緊張にも二種類あります。
良い緊張と悪い緊張です。
良い緊張。
これは緊張感を感じながらも、
程よく高揚して寧ろ高い集中力を生みます。
一方で、悪い緊張。
これは過度な緊張感で焦りや思考停止を生み、
いつも通りの事すらできなくなります。
もちろん受験で失敗する緊張は悪い緊張です。
これは悪い緊張で落ちるくらいの、
瀬戸際で戦っていた自分が悪い。
そのような緊張への対処は、
受験前に行うことができるから。
悪い緊張に襲われない、
最悪襲われても受かる。
そういう準備をするのが、
受験勉強です。
「試験が楽しみ」
圧倒的に学力的余裕があれば、
悪い緊張とは縁が無くなります。
また最悪緊張による失点があっても、
それ込みで受かるようにしておく。
ボーダーギリギリじゃなくて、
合格点∔2割取るのを、
当たり前にしておくなど。
そうすれば当日少しくらい、
緊張で失点しても、
問題なく合格することができます。
ここまで出来なかったなら、
落ちたのは緊張のせいではなく、
自分の問題としか言えないでしょう。
単に実力不足なだけです。
・過去問では「合格点+2割」取れるようになるべき理由はこちら⇩
過去問で合格点なんて当たり前だろ?本当に受かりたければ「合格点+2割」を楽勝にしようぜ!
A判定取ったうえで確実に受かるには
常に俯瞰し慢心しない
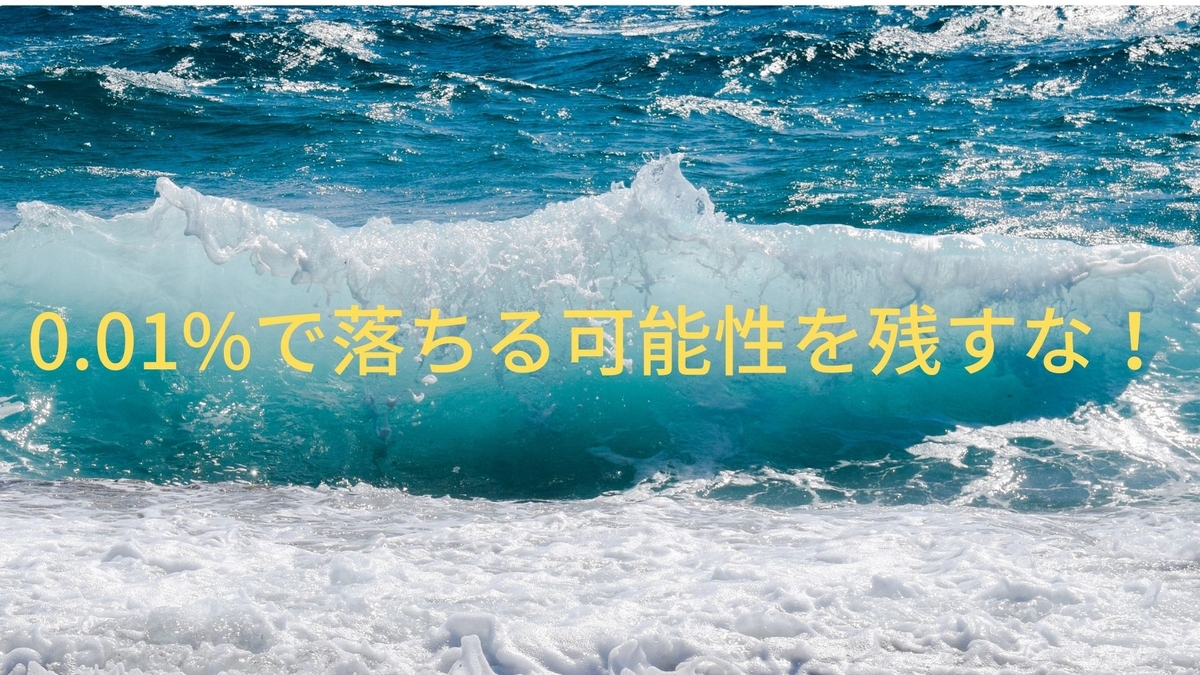
ここまでA判定でも落ちるという話と、
その原因について話をしてきました。
じゃあ結局どうしたら良いのか?
それは慢心せず、
常に自分を俯瞰し、
とにかく現状に満足しないことだと思います。
A判定取るのは立派な事です。
でも所詮は模試。
模試でA判定取るために、
勉強しているのではありませんよね?
志望校合格への道のりの中に、
模試のA判定があるに過ぎません。
少し模試の成績が良いからと天狗にならず、
自分に足りない物をどん欲に見つける。
ほんの少しの落ちる可能性をすら排除する。
そういう心構えで勉強に取り組むべきです。
絶対落ちないというのは、
厳密にはあり得ないんでしょう。
それでも落ちる可能性を、
1%・0.1%・0.01%と限りなく減らしていく。
過去問で満点取れるようになれば、
事故や病気で重篤にならない限りは受かります。
ここまで持って行けないなら、
それは自分に問題があります。
常にそのレベルを目指して、
勉強に取り組みましょう。
模試の判定には貪欲に、でも慢心せずに
さいごに
志望校に受かりたいなら、
模試ではA判定を目指すべきです。
それは学力を図る重要な指標にはなります。
でも、そこに驕ったら終わり。
結果に驕らず常に上を、
完璧を目指して勉強して下さい。
「一ミリも隙を与えない状態を目指す」
これは口で言うほど簡単じゃありません。
もしかしたら不可能な事なのかもしれませんが、
それくらいの気持ちで勉強すれば、
自ずと結果は付いてきますからね。
⇒【決着】絶対こっち!模試OR過去問どっちを信用するべきか?はこちら
⇒【即解決】過去問が解けない!うまくいかない時にやるべき3つの考え方と注意事項はこちら
⇒【勝ちパターン】過去問を繰り返し解く意味はこれ!これで合否が分かれちゃう・・・はこちら